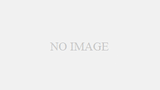「私の気分は国を立つ時すでに厭世的になっていました。他とは頼りにならないものだという観念が、その時、骨の中まで染しみ込んでしまったように思われたのです。私の心は沈鬱でした。鉛を呑んだように重苦しくなる事が時々ありました。それでいて私の神経は、今いったごとくに鋭く尖とがってしまったのです。
「奥さんのこの態度が自然私の気分に影響して来ました。しばらくするうちに、私の眼はもとほどきょろ付かなくなりました。自分の心が自分の坐わっている所に、ちゃんと落ち付いているような気にもなれました。要するに奥さん始め家うちのものが、僻だ私の眼や疑い深い私の様子に、てんから取り合わなかったのが、私に大きな幸福を与えたのでしょう。私の神経は相手から照り返して来る反射のないために段々静まりました。
奥さんは心得のある人でしたから、わざと私をそんな風うに取り扱ってくれたものとも思われますし、また自分で公言するごとく、実際私を鷹揚だと観察していたのかも知れません。私の心が静まると共に、私は段々家族のものと接近して来ました。奥さんともお嬢さんとも笑談をいうようになりました。茶を入れたからといって向うの室へ呼ばれる日もありました。また私の方で菓子を買って来て、二人をこっちへ招いたりする晩もありました。
私は思い切って奥さんにお嬢さんを貰い受ける話をして見ようかという決心をした事がそれまでに何度となくありました。けれどもそのたびごとに私は躊躇して、口へはとうとう出さずにしまったのです。断られるのが恐ろしいからではありません。もし断られたら、私の運命がどう変化するか分りませんけれども、その代り今までとは方角の違った場所に立って、新しい世の中を見渡す便宜も生じて来るのですから、そのくらいの勇気は出せば出せたのです。
彼の重々しい口から、彼のお嬢さんに対する切ない恋を打ち明けられた時の私を想像してみて下さい。私は彼の魔法棒のために一度に化石されたようなものです。口をもぐもぐさせる働きさえ、私にはなくなってしまったのです。
その時の私は恐ろしさの塊かたまりといいましょうか、または苦しさの塊りといいましょうか、何しろ一つの塊りでした。石か鉄のように頭から足の先までが急に固くなったのです。呼吸をする弾力性さえ失われたくらいに堅くなったのです。幸いな事にその状態は長く続きませんでした。私は一瞬間の後のちに、また人間らしい気分を取り戻しました。そうして、すぐ失策しまったと思いました。先を越されたなと思いました。
ある日私は突然往来でKに肉薄しました。私が第一に聞いたのは、この間の自白が私だけに限られているか、または奥さんやお嬢さんにも通じているかの点にあったのです。私のこれから取るべき態度は、この問いに対する彼の答え次第で極めなければならないと、私は思ったのです。すると彼は外の人にはまだ誰だれにも打ち明けていないと明言しました。私は事情が自分の推察通りだったので、内心嬉しがりました。
その時私の受けた第一の感じは、Kから突然恋の自白を聞かされた時のそれとほぼ同じでした。私の眼は彼の室の中を一目見るや否いなや、あたかも硝子で作った義眼のように、動く能力を失いました。私は棒立に立たち竦すくみました。それが疾風のごとく私を通過したあとで、私はまたああ失策しまったと思いました。もう取り返しが付かないという黒い光が、私の未来を貫いて、一瞬間に私の前に横たわる全生涯を物凄ごく照らしました。そうして私はがたがた顫え出したのです。
それでも私はついに私を忘れる事ができませんでした。私はすぐ机の上に置いてある手紙に眼を着けました。それは予期通り私の名宛になっていました。私は夢中で封を切りました。しかし中には私の予期したような事は何にも書いてありませんでした。私は私に取ってどんなに辛つらい文句がその中に書き列つらねてあるだろうと予期したのです。そうして、もしそれが奥さんやお嬢さんの眼に触れたら、どんなに軽蔑されるかも知れないという恐怖があったのです。私はちょっと眼を通しただけで、まず助かったと思いました。(固もとより世間体の上だけで助かったのですが、その世間体がこの場合、私にとっては非常な重大事件に見えたのです。)
手紙の内容は簡単でした。そうしてむしろ抽象的でした。自分は薄志弱行で到底行先の望みがないから、自殺するというだけなのです。それから今まで私に世話になった礼が、ごくあっさりとした文句でその後あとに付け加えてありました。世話ついでに死後の片付方かたづけかたも頼みたいという言葉もありました。奥さんに迷惑を掛けて済まんから宜しく詫わびをしてくれという句もありました。国元へは私から知らせてもらいたいという依頼もありました。必要な事はみんな一口ずつ書いてある中にお嬢さんの名前だけはどこにも見えません。私はしまいまで読んで、すぐKがわざと回避したのだという事に気が付きました。しかし私のもっとも痛切に感じたのは、最後に墨すみの余りで書き添えたらしく見える、もっと早く死ぬべきだのになぜ今まで生きていたのだろうという意味の文句でした。
襖に迸ほとばしっている血潮を始めて見たのです。
「私は突然Kの頭を抱かかえるように両手で少し持ち上げました。私はKの死顔が一目見たかったのです。しかし俯伏うつぶしになっている彼の顔を、こうして下から覗のぞき込んだ時、私はすぐその手を放してしまいました。慄ぞっとしたばかりではないのです。彼の頭が非常に重たく感ぜられたのです。私は上から今触た冷たい耳と、平生に変らない五分刈ごぶがりの濃い髪の毛を少時しばらく眺ながめていました。私は少しも泣く気にはなれませんでした。私はただ恐ろしかったのです。そうしてその恐ろしさは、眼の前の光景が官能を刺して起る単調な恐ろしさばかりではありません。私は忽然と冷たくなったこの友達によって暗示された運命の恐ろしさを深く感じたのです。
私は何の分別ふんべつもなくまた私の室へやに帰りました。そうして八畳の中をぐるぐる廻まわり始めました。私の頭は無意味でも当分そうして動いていろと私に命令するのです。私はどうかしなければならないと思いました。同時にもうどうする事もできないのだと思いました。座敷の中をぐるぐる廻らなければいられなくなったのです。檻の中へ入れられた熊のような態度で。
私は時々奥へ行って奥さんを起そうという気になります。けれども女にこの恐ろしい有様を見せては悪いという心持がすぐ私を遮さえぎります。奥さんはとにかく、お嬢さんを驚かす事は、とてもできないという強い意志が私を抑えつけます。私はまたぐるぐる廻り始めるのです。
私はその間に自分の室の洋燈ランプを点つけました。それから時計を折々見ました。その時の時計ほど埒の明かない遅いものはありませんでした。私の起きた時間は、正確に分らないのですけれども、もう夜明よあけに間まもなかった事だけは明らかです。ぐるぐる廻まわりながら、その夜明を待ち焦こがれた私は、永久に暗い夜が続くのではなかろうかという思いに悩まされました。
我々は七時前に起きる習慣でした。学校は八時に始まる事が多いので、それでないと授業に間に合わないのです。下女はその関係で六時頃に起きる訳になっていました。しかしその日私が下女を起しに行ったのはまだ六時前でした。すると奥さんが今日は日曜だといって注意してくれました。奥さんは私の足音で眼を覚ましたのです。私は奥さんに眼が覚めているなら、ちょっと私の室へやまで来てくれと頼みました。奥さんは寝巻の上へ不断着の羽織を引ひっ掛かけて、私の後あとに跟ついて来ました。私は室へはいるや否いなや、今まで開いていた仕切りの襖ふすまをすぐ立て切りました。そうして奥さんに飛んだ事ができたと小声で告げました。奥さんは何だと聞きました。私は顋で隣の室を指すようにして、「驚いちゃいけません」といいました。奥さんは蒼い顔をしました。「奥さん、Kは自殺しました」と私がまたいいました。奥さんはそこに居竦いすくまったように、私の顔を見て黙っていました。その時私は突然奥さんの前へ手を突いて頭を下げました。「済みません。私が悪かったのです。あなたにもお嬢さんにも済まない事になりました」と詫あやまりました。
そこはそのままにしておいて、雨戸を開けてくれと私にいいました。
それから後あとの奥さんの態度は、さすがに軍人の未亡人だけあって要領を得ていました。私は医者の所へも行きました。また警察へも行きました。しかしみんな奥さんに命令されて行ったのです。奥さんはそうした手続の済むまで、誰もKの部屋へは入いれませんでした。
Kは小さなナイフで頸動脈を切って一息に死んでしまったのです。すぐ仏臭ほとけくさい烟で鼻を撲うたれた私は、その烟の中に坐すわっている女二人を認めました。私がお嬢さんの顔を見たのは、昨夜来この時が始めてでした。お嬢さんは泣いていました。奥さんも眼を赤くしていました。事件が起ってからそれまで泣く事を忘れていた私は、その時ようやく悲しい気分に誘われる事ができたのです。私の胸はその悲しさのために、どのくらい寛くつろいだか知れません。 Kを雑司ヶ谷へ葬ほうむったところで、どのくらいの功徳くどくになるものかとは思いました。けれども私は私の生きている限り、Kの墓の前に跪ひざまずいて月々私の懺悔ざんげを新たにしたかったのです。