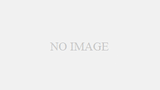- 私わたくしはその人を常に先生と呼んでいた。だかここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。これは世間を憚かる遠慮というよりも、その方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起すごとに、すぐ「先生」といいたくなる。筆を執も心持は同じ事である。
- 私が先生と知り合いになったのは鎌倉である。その時私はまだ若々しい書生であった。
- 次の日私は先生の後あとにつづいて海へ飛び込んだ。そうして先生といっしょの方角に泳いで行った。二丁ほど沖へ出ると、先生は後ろを振り返って私に話し掛けた。広い蒼い海の表面に浮いているものは、その近所に私ら二人より外ほかになかった。そうして強い太陽の光が、眼の届く限り水と山とを照らしていた。私は自由と歓喜に充た筋肉を動かして海の中で躍り狂った。先生はまたぱたりと手足の運動を已めて仰向けになったまま浪の上に寝た。私もその真似をした。青空の色がぎらぎらと眼を射るように痛烈な色を私の顔に投げ付けた。「愉快ですね」と私は大きな声を出した。
- しばらくして海の中で起き上がるように姿勢を改めた先生は、「もう帰りませんか」といって私を促した。私はその晩先生の宿を尋ねた。宿といっても普通の旅館と違って、広い寺の境内にある別荘のような建物であった。そこに住んでいる人の先生の家族でない事も解かった。
- 私が先生先生と呼び掛けるので、先生は苦笑いをした。私はそれが年長者に対する私の口癖くちくせだといって弁解した。すると奥さんらしい人が代って出て来た。美しい奥さんであった。先生は例月その日になると雑司ヶ谷の墓地にある或ある仏へ花を手向に行く習慣なのだそうである。「たった今出たばかりで、十分になるか、ならないかでございます」と奥さんは気の毒そうにいってくれた。
- 私くしは墓地の手前にある苗畠の左側からはいって、両方に楓を植え付けた広い道を奥の方へ進んで行った。するとその端に見える茶店の中から先生らしい人がふいと出て来た。私はその人の眼鏡の縁ふちが日に光るまで近く寄って行った。そうして出し抜けに「先生」と大きな声を掛けた。先生は突然立ち留まって私の顔を見た。
「どうして……、どうして……」先生は同じ言葉を二遍繰り返した。その言葉は森閑した昼の中に異様な調子をもって繰り返された。私は急に何とも応られなくなった。「私の後を跟つけて来たのですか。どうして……」
先生の態度はむしろ落ち付いていた。声はむしろ沈んでいた。けれどもその表情の中には判然いえないような一種の曇りがあった。私は私がどうしてここへ来たかを先生に話した。「誰の墓へ参りに行ったか、妻がその人の名をいいたか」「いいえ、そんな事は何もおっしゃいません」「そうですか。――そう、それはいうはずがありませんね、始めて会ったあなたに。いう必要がないんだから」先生はようやく得心したらしい様子であった。しかし私にはその意味がまるで解らなかった。