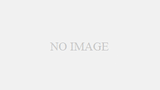投稿記事「文学散歩」を書くにあたり、樋口一葉を外すわけにはいかない。しかし私しは通り一遍の樋口一葉しか知らない。従って「Wikipedia」で勉強することにした。それを書く。
出生から少女時代
一葉は1872年5月2日(旧暦明治5年3月25日)、現在の東京都千代田区内幸町の東京府庁構内官舎で、東京府役人の樋口則義と多喜の二男二女の次女として誕生した。。
幼児期から利発で言葉が出るのも早く物覚えがよかったという。明治10年、満4歳10か月で公立本郷小学校に入学するが、幼少のためにほどなく退学し、半年後、吉川富吉が始めた私立吉川学校に入学した。一葉の日記『塵之中』によれば、幼少時代は手毬や羽根つきなど同年代の子供の遊びに興味がなく、読書を好み草双紙の類いを読み耽っていた。曲亭馬琴「南総里見八犬伝」を3日で読破したとも伝えられている。
明治14年、上野元黒門町の私立青海学校に転校する。ここで初めて和歌を習う。明治16年、高等科第四級を首席で卒業するも、上級に進まずに退学した。これは母・多喜が、女性に学業は不要だと考えていたからだという。
「萩の舎」に入門
父・則義は向学心やまない娘のため、和歌を習わせた。明治19年、中島歌子の歌塾「萩の舎」に入門。ここでは和歌のほか書や王朝文学の講読を学んだ。萩の舎は当時、旧体制名家、明治政府の政治家・軍人の夫人や令嬢らが通い、門人は千人を超える歌塾だった。士族とはいえ下級役人の娘だった一葉は、この発会の歌会で最高点を取っている。
このように入門当初は才気煥発なところを見せていた一葉だったが、周囲との格差から次第に内向的になった。
兄と父の死、生活苦
一葉は17歳で樋口家を背負うことになった。
家賃の安い借家へ移ろうと現在の東京都文京区に引っ越し、母と妹と3人での針仕事や洗い張り、下駄の蝉表作りなどの賃仕事をするが、それだけでは足りず、方々に借金を繰り返す苦しい生活を強いられる。
小説家への道
一葉は、原稿料を得るため明治22年頃より小説を書こうと決意する。
一葉は、東京朝日新聞専属作家半井桃水に師事する。そして、一葉を東京朝日新聞主筆に紹介する。しかし一葉の小説は採用されず、新聞小説で原稿料を得ようとした一葉は落胆する。
幸田露伴風の理想主義的な小説『うもれ木』を雑誌『都之花』に発表。初めて原稿料11円50銭を受け取る。このうち6円は借金の返済に充てられた。
奇跡の14ヶ月
『文学界』創刊号に『雪の日』を発表。その後、筆が進まない一葉は、生活苦打開のため明治26年7月、吉原遊郭近くの現在の台東区竜泉一丁目で荒物と駄菓子を売る雑貨店を開く。この時の経験が、後に代表作となる小説『たけくらべ』の題材となっている。年末、『琴の音』を『文学界』に発表。明治27年5月には店を引き払い、現在の文京区西片一丁目)に転居する。
吉原遊郭近くで荒物と駄菓子を売る雑貨店を営んでいたのは、8ヶ月である。私くしは思う「吉原遊郭の閉ざされた女性の生活は、一葉にとってはこの時代のテーマパークの出来事」と捉えているにすぎない、
萩の舎と交渉し、月2円の助教料が得られるようになった。
同年12月に『大つごもり』を『文学界』に発表する。明治28年には半井桃水から博文館の大橋乙羽を紹介される。博文館は明治20年に創業された出版社で、『太陽』『文藝倶楽部』などを発刊し、春陽堂と並び出版界をリードする存在であった[36]。大橋乙羽は作家として活動していたが、博文館の館主・大橋佐平に認められ、佐助の長女大橋ときを妻に迎える[36]。大橋夫妻は一葉に活躍の場を与え経済的にも支援しており、大橋ときは一葉に入門して和歌を学んでいる[36]。
乙羽は明治28年同年3月の一葉宛書簡で小説の寄稿を依頼している[36]。この年は1月から『たけくらべ』を7回にわたり発表し、その合間に乙羽の依頼で『ゆく雲』を執筆したほか、大橋ときの依頼で『経つくえ』を書き改めた上で『文藝倶楽部』に再掲載させた[37]。このほか『にごりえ』『十三夜』などを発表している。『大つごもり』から『裏紫』にかけての期間を、一葉研究家の和田芳恵は「奇跡の14ヶ月」と呼んだ[21]。
なお、明治28年は7月12日に父・則義の七回忌法要があるため、一葉は大橋ときに法要のための原稿料前借りを申し出ている。乙羽はこれを了承し、一葉は7月下旬に未完成の『にごりえ』原稿は届け、8月2日には残りの原稿が渡された[38]。
1895年(明治28年)4月から樋口家には馬場孤蝶や島崎藤村など『文学界』同人や斎藤緑雨といった文筆家などの来客が毎日訪れるようになり、文学サロンのようになった。一葉は着るものにも困る生活であったが、来客を歓迎し、鰻や寿司を取り寄せてふるまった[39]。
早世
1896年(明治29年)には『文藝倶楽部』に『たけくらべ』が一括掲載されると、森鷗外や幸田露伴は同人誌『めさまし草』で一葉を高く評価した。
5月には『われから』を『文藝倶楽部』で、『通俗書簡文』を『日用百科全書』で発表。しかし一葉は治療法が当時なかった肺結核が進行しており、8月に斎藤緑雨の依頼を受けた(自らも医者である)森鷗外が、当代随一と言える樫村清徳、青山胤通らの医師を頼み往診に向かわせたが、恢復が絶望的との診断を受けた[40]。
11月23日、丸山福山町の自宅において、24歳と6か月で死去[41]。自宅跡には、一葉終焉の地であることを示す石碑が建てられている[42]。
葬儀は11月25日に他人にきてもらうだけの営みができないという理由で、身内だけ十数人で築地本願寺で質素に行われた。
作品解題
小説
- 闇桜(1892年3月『武蔵野』) 幼馴染の園田良之助と中村千代の淡い初恋を描いたもの。千代は良之助への忍ぶ恋情に悩み、ついに病床に臥すようになり儚くなってしまうのであった。結末の「風もなき軒端の桜ほろほろとこぼれて、夕やみの空鐘の音かなし」が題名の由来である。
- 別れ霜(1892年4月『改進新聞』) 松沢芳之助と新田高は父親同士が義理の兄弟の呉服商であった。ところが高の父運平の姦計で松沢家は没落、生活に窮乏して芳之助は人力車の車夫に身を落とした。一方、高には医学士某との縁談が持ち上がり、父運平も乗り気になった。ある日、音曲会の帰りに高は偶然芳之助の車に乗ることとなり、後の逢引の日取りも決めたが、その日に芳之助が現れなかったので高は芳之助親子の住む陋屋を訪ねるが、芳之助の父にすげなく追い払われてしまった。行く末を儚んだ芳之助と高は新田家の墓所で心中を図るが高だけが生き残ってしまった。お高は自宅に軟禁され自殺しないように監視されるが、ある夜芳之助のあとを追うため失踪してしまうのであった。
- たま欅(1892年4月『武さし野』) 大身旗本の子孫であるが両親を失い孤独な青柳いと子に忠節を尽くしていたのは、家来筋の松野雪三であった。或る夏の夕暮れ、いと子は隣家の植木屋に避暑に来ていた子爵の息子竹村緑と垣根越しに偶然顔をあわせ二人とも恋に落ちてしまった。一方、雪三のいと子への忠誠心はやがて激しい恋情にかわり、雪三は竹村家から申し込みのあったいと子の縁談を独断で断ってしまった。いと子は雪三と緑両方の恋情の板挟みに苦しみ自害して果てるのであった。
- 五月雨(1892年7月『武さし野』) 仕える令嬢の恋の使者を務めた腰元、その相手は以前故郷で将来を誓いあった幼馴染だった。返事のないまま男は行方知れずになったが、あるとき寺の前にたたずむ若い雲水の顔を見て、二人の女はあっと声を上げた。
- 経づくえ(1892年10月『甲陽新報』) 自分の病院で亡くなった女の娘を援助する医学士の松島忠雄。娘のお園はどうしてもこの男を好きになれぬまま、医師は札幌に転勤して行ってしまい、そこで病死する。お園はその後縁もあったが、医学士に操を立て経机に向かい菩提を弔っている。
- うもれ木(1892年11月『都之花』) 志は高いが赤貧に苦しむ陶芸家の入江藾三と妹お蝶。10年前に恩師の金を持ち逃げした同門の篠原辰雄は今や慈善家となって前非を悔いており、2人は師の墓前で仲直りする。しかし篠原は実直な藾三を騙し、自分を慕うお蝶を利用して自らの目的を遂げようとする。
- 暁月夜(1893年2月『都之花』) 男嫌いの令嬢に興味を持った学生の敏は庭男となって子爵家に入り込み、弟の甚之助を手なずけ、その仲介で彼女に恋文を渡すが、令嬢は封をも切らず、東京を離れ鎌倉の別荘に移ると言い出す。最後の別れのため夜忍び込んできた敏に、令嬢は自分は実は道ならぬ恋ゆえに生まれてきたと出生の秘密を語り、同じ過ちをせず勉学に励めと説く。
- 雪の日(1893年3月『文學界』)
- 琴の音(1893年12月『文學界』)
- 花ごもり(1894年2月『文學界』) 瀬川与之助は、母お近、幼い頃両親を亡くした従妹お新との、他に身寄りのない3人暮らし。若い2人はこのまま一生を仲よく過ごせたらと思っているが、息子の出世を願う母親は田原家令嬢との結婚話に心を動かされる。令嬢を紹介した月琴の師匠お辰の計らいで優柔不断の与之助をすかしてこれに同意させ、邪魔なお新は田舎に住む絵師のもとへ下働きとして送り出すことにする。お新が田舎行きを拒まなかったのは、絵の好きな与之助のため自分も習えると思ったから。素直なお新は企みがあるとはつゆ知らず、上野駅を発って行く。
- 暗(やみ)夜(1894年7月『文學界』) 主人公お蘭は婚約者に裏切られ、涙と怨念の中で暮らしている。お蘭の屋敷近くで、その婚約者の車に轢かれた直次郎が屋敷に運び込まれ、直次郎はお蘭に恋をする。お蘭から婚約者の裏切りを聞いた直次郎は婚約者の暗殺を決心する。
- 大つごもり(1894年12月『文學界』)
- たけくらべ(1895年1月 – 1896年1月『文學界』)
- 軒もる月(1895年4月『毎日新聞』) 月の夜、人妻が寝る子を眺めながら、以前仕えていた桜町の殿からもらった12通の恋文を前にして思い悩んでいる。女は決心して初めて手紙の封を切り、読み終わると切り刻んで火の中にくべてゆく。
- ゆく雲(1895年5月『太陽』)
- うつせみ(1895年8月『読売新聞』) 閑静な土地の空き家に若い病人の雪子が移り住んできた。精神の病いで、一月ごとに駄々をこねて転宅を繰り返しているのである。原因は雪子が振った植村が自殺したことに罪悪感を感じているらしい。良家の一粒種で両親も気が気でないが、雪子の狂気は募ってゆく。
- にごりえ(1895年9月『文藝倶楽部』)
- 十三夜(1895年12月『文藝倶楽部』) 官吏に嫁ぎ、一子を儲けたものの、夫の虐待に耐えかねて実家に逃げ帰ったお関。しかし、父はそんなお関を諭し、婚家に帰らせる。その帰り道、上野の森で拾った人力車の車夫は、かつてのお関の幼馴染で、煙草屋の一人息子録之助だった。互いに淡い恋心を抱いていた2人だったが、お関の結婚後、録之助は自暴自棄になって家産を食いつぶし、車夫にまで堕ちていたのであった。
- この子(1896年1月『日本乃家庭』) 強情でわがままに育った主人公が、新婚の裁判官の夫とそりが合わなくなり、縁組みをした親を恨んだり、子供が元気に生まれてきたことまで神に呪ったりする。しかし赤ん坊の笑顔を見ているうちに心が和みだし、自分のいけなかったところまでがはっきり見えてくるようになる。まさに我が子は人生で最大の師である。
- わかれ道(1896年1月『国民之友』) お針仕事が稼業のお京の長屋に傘屋の油引きの吉三が通ってくる。天涯孤独の吉三は仲間から「一寸法師」とあざけられ、つまらない人生を送っているが、行けば餅をごちそうしてくれる姉のようなお京だけが生きてゆく支えのようなもの。ある日お京から人の妾になることを告げられた吉三は、自ら望まぬところへ行くのはおよしとすねるように訴える。
- われから(1896年5月『文藝倶楽部』) 大蔵省の下級役人金村与四郎の幼なじみの妻美尾は人からうらやまれるほどの美人だが、夫の給料の少ないのが恥ずかしく着飾った人を見るたび不満が募る。勉強して出世してくれと訴えるが夫は逆に腹を立てるだけ。女の子が出来た直後、子供を残して突然家出をしてしまう。それから25年の間に、与四郎は一念発起して金を貯め50歳を待たずに亡くなるが、そのおかげで娘の町子は恭助という婿をもらい、気ままな暮らしをしている。ただ子供ができず、夫の女遊びも止まないまま、捨てられるのではという不安な毎日だったが、ある大掃除の日、召使いたちの噂話を壁ごしに聞いて旦那様には妾と10歳になる子供があることを知る。癇癪を起こし出した町子の介抱に書生の千葉が日夜励んだことがかえって悪い噂を近所にまくことになり、町子は突然、夫から別居を言い渡される。